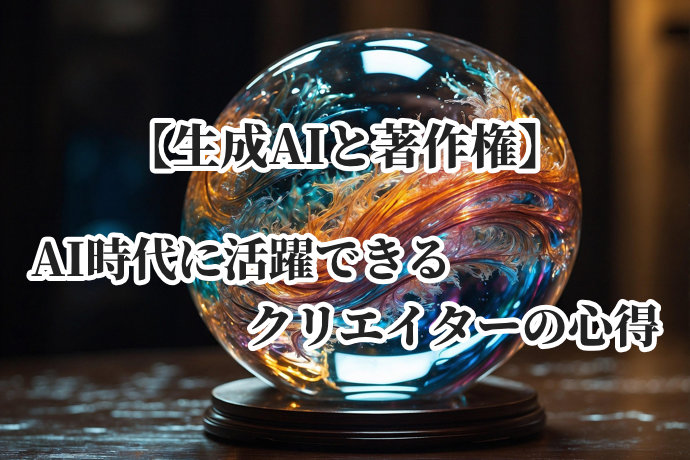

生成AIは、現在も非常に速いスピードで進化しつづけています。
人間と同等レベルの高いクオリティで生成することも十分に可能です。
だからこそ、成果物に対する著作権の認識は非常に重要です。
著作権は、クリエイターに付与される法的な権利です。
その権利を侵害することは、あってはなりません。
この記事では、生成AIと著作権について、具体的なリスクと対策について解説します。
AI時代に活躍できるクリエイターとして、適切な心得を身につけておきましょう!
まずは、著作権について簡単に紹介します。
すでにご存知かと思いますが、具体的にお話ししますね。
著作権とは、創作された「表現」に対して自動的に与えられる権利です。
作者の人格や利益を守る目的で存在しています。
主な対象は、文学、音楽、絵画、写真、映像、プログラムなどの創作物です。
「思想・感情を創作的に表現したもの」が保護されます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 著作財産権 | 著作物を「複製」「公開」「販売」「翻訳」などする権利 (他者に使用を許諾でき、対価も得られる) |
| 著作者人格権 | 著作者の名誉や意図を守るための権利。譲渡や放棄はできない (例:勝手に改変されたくない) |
個人が二次創作できる背景には、著作権者が「黙認」している場合もあります。
しかし、それは法律的に許可されているわけではありません。
あくまでも、実際には「許可を得ていない」状態です。
たとえば、YouTubeやSNSでの二次創作などが許されていることもあります。
これも、あくまで権利者が何らかの理由で黙認しているだけです。
権利者が許可しない限り、厳密には著作権侵害になり得る行為です。
このような認識があいまいだと、著作権の境界線がブレてしまいます。
二次創作は、コンテンツへの愛情から生まれるものも多いと思います。
だからこそ、適切な著作権の認識が必要です。
次に、どのような著作権リスクがあるかを整理してみましょう。
生成AIが取り扱うコンテンツの種類ごとにまとめて紹介します。
テキスト生成AIとは、チャットGPTなどのようにテキストを出力するAIのことです。
主に文章作成や、チャットでの対話型として動作します。
NLPやLLMといった仕組みで、とても創造的な対話や文章表現が可能です。
画像生成AIとは、プロンプト(指示)をもとに画像を出力するAIのことです。
ハイクオリティな生成が可能であり、人間が描いたイラストと遜色ないくらいです。
現在では、拡散モデル(Diffusion Models)が主流となっています。
単語で指定するプロンプトや、DALL-Eのように対話型で利用できるモデルがあります。
音楽生成AIとは、与えられた指示やデータを基に音楽を作成するAIのことです。
メロディやハーモニー、リズムなどを自動的に生成可能です。
ジャンルや雰囲気に応じた音楽など、多彩な表現を提供します。
AIが生成した音楽は、プロの作曲家が手がけたものに近いほどのクオリティです。
動画生成AIとは、テキストや画像を元に自動的に動画を生成するAIのことです。
たとえば、SoraのようなAIは、プロンプトで指定されたシーンやキャラクターを基に、リアルな動きや表現を持ったアニメーションを作り出します。
この技術は、CGアニメーションの制作過程を大幅に効率化します。
短期間で高品質な動画を生成することが可能です。
さて、それではなぜ生成AIが著作権を侵害してしまう可能性があるのでしょうか?
たとえ意図していなくても、著作権を侵害するのは違法です。
信頼されるAIクリエイターとして、著作権の遵守は必須となります。
生成AIが著作権を侵害する要因は、大きく以下の4つに分類されます。
一つずつ、さらに詳しく見ていきましょう。
| 事例 | 内容 |
|---|---|
| イラストレーター抗議(2023年) | 自分の絵柄がAI画像に模倣されたとして、Midjourneyユーザーに抗議しSNSで拡散 |
| ChatGPTの要約が著作物と一致 | 雑誌記事の要約を依頼 → 元の文章と「ほぼ同一」の表現が出力されてしまった |
| AI生成キャラが商標権侵害 | 生成されたロゴが、既存ブランドのロゴに酷似していたことから使用中止に |
当然のことですが、著作権侵害は非常に問題のある行為です。
だからこそ、リスクを事前に把握して適切に対策することが重要になります。
生成AIを安全に活用するためには、以下の3段階で対策を講じることが有効です。
ここからは、具体的な対策方法をより詳しくお伝えしていきます。
まずは基本となる5つの対策です。
これは、AIを使用する前に事前に把握しておくと良いでしょう。
次に、具体的な対策の手順を3つのステップでご紹介します。
「少年が冒険するアニメ風イラスト。青い空と仲間の雰囲気を感じるように」
「透明感のある空と海。幻想的で美しい光を表現して」
ポイントは、作風の「雰囲気」や「質感」を抽象的に表現することです。
「ドラゴンボール風のイラストを生成して」
「新海誠っぽい映像で海を描いて」
「ワンピースのルフィに似たキャラを作って」
これらは、特定の著作物や作風を模倣させる指示です。
商用利用では、著作権侵害になるリスクがあります。
類似画像検索(Google画像検索、TinEyeなど)で既存作品と酷似していないか調査
文章の場合は「Copyscape」「AI Text Classifier」などで他作品との一致率を確認
実在の企業ロゴ・人物・建築物が含まれていないか確認
商用利用前に必ず自分の解釈を加えて再編集する
Midjourneyで生成した画像をそのままSNSで公開
フォロワーから「この構図、〇〇先生の作品と同じでは?」と指摘
削除&謝罪へ
| ツール・素材サイト | 商用利用 | 備考 |
|---|---|---|
| ChatGPT(Plus) | ○ | テキスト利用は可能。ただし出力責任は利用者側に |
| DALL-E 3 | ○ | OpenAI提供。生成物に関する著作権は利用者に |
| Unsplash / Pixabay | ○ | フリー素材だが、一部制限あり(ブランドロゴなど) |
| ILLUSTAC / Adobe Firefly | △ | コンテンツによってライセンス条件が異なる |
最も良い方法は、あなたのオリジナルコンテンツを作成することです。
オリジナルコンテンツは、著作権回避の明確な手段だといえます。
それと同時に、ビジネス価値や信頼性の源泉にもなります。
具体的な利点や価値について、さらに詳しくお伝えしていきます。
同じキーワードで複数記事が存在していても、「自分の実体験+AI知見」で構成された記事が、SEOでも上位表示されやすい。
ChatGPTと自分の知識で作った記事を、再構成して「ChatGPT活用ノウハウ講座」として販売する。
イラストAIを使っても、「自分の物語世界観に沿ったキャラクター」として丁寧に描き直せば、ファンが付くようになる。
最後に、生成AIと著作権について、ケース別に一覧表でまとめます。
どんな注意点があって、どのように対策するかという指針になるでしょう。
| ケース | 注意点 | 対応策 |
|---|---|---|
| ブログ記事にAI文章を使う | 表現が他者の文章と類似するリスク | 自分の視点を加え、体験や意見を混ぜて構成する |
| LPの画像をAI生成で作成 | キャラ・構図が既存作品と酷似する場合あり | 抽象化した指示+手動で構図修正 or 加筆修正 |
| YouTubeサムネにAI画像使用 | 著名人・ブランドロゴに注意 | 肖像権・商標権がないフリー素材か、自作キャラを使う |
| eBookをAIで書く | AI生成だけでは独創性不足 | 自分の分析や事例を豊富に取り入れることで独自性UP |
生成AIの進化により、法整備も今まさに追いつこうとしている段階です。
だからこそ今は、クリエイターやビジネス活用者が「自律的な配慮と創意」をもって、AIを活かすフェーズにあるとも言えます。
生成AIはあくまでも道具です。
大切なのは、それを通してあなた自身の創造性がどう輝くかです。
はい、AIが既存の書籍や記事の表現をそのまま再現した場合、著作権侵害と判断されることがあります。
要約や引用でも、自分の視点や編集を加えることが重要です。
“○○風”といった特定の作家や作品のスタイルを模倣するプロンプトは、著作権侵害や商標権の問題に発展する可能性があります。
特に商用利用時は避けた方が良いでしょう。
AIの学習データに著作物が含まれていても、出力内容が著作権を侵害しない限りは原則として問題ありません。
ただし、欧州などでは学習時に著作権管理が求められ始めています。
はい。
利用規約の確認、プロンプトの工夫、類似性チェック、編集による独自性の追加、信頼あるツールの使用が基本対策です。
使用は可能ですが、著名人の顔や企業ロゴが含まれていないか確認しましょう。
フリー素材や自作キャラクターを使用するのが安全です。
生成AIの利用規約によりますが、基本的に著作権は利用者に帰属します。
ただし、元データや出力内容に他人の著作物が含まれていると、著作権侵害の可能性があります。
商用利用可能なAIツールで、他人の作風やキャラクターを模倣していない場合は可能です。
念のため構図やスタイルの類似性に注意し、編集や再構成を加えるのが望ましいです。
AI生成物に自分の表現や構成を加えて再編集することが大切です。
独自性を高めることで法的リスクを下げ、SEOやブランド力にもつながります。

【Nexus AI 代表】Web制作・デザイン・マーケティング・コンサルティング等の経験を積み、日本 AIコミュニティ Nexus AIを立ち上げる。AI技術を活用して、コミュニティ運営に役立てている。
変化を起こし続けるなら、その人生には意味がある。
よく使うAI:OpenAI(ChatGPT, OpenAI APIなど)
好きなゲーム:ウィッチャーシリーズ、サイバーパンク2077、Forza Horizonシリーズ、その他多数

Web制作・デザイン・マーケティング・コンサルティング等の経験を積み、ChatGPTコミュニティ Nexus AIを立ち上げる。AI技術を活用して、コミュニティ運営に役立てている。