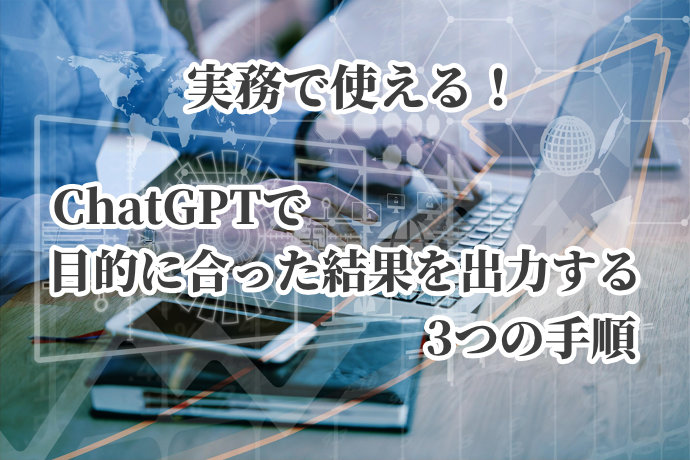

生成AIの出力が「なぜか思った通りの文章にならない…」と感じたことはありませんか?
チャットGPTは非常に高性能なテキスト生成AIです。
しかし、質問によっては目的に合った出力が得られるわけではありません。
そこで重要なのが、「明確なプロンプト設計」と「フィードバックによる微調整」です。
この記事では、実務でもすぐに使えるチャットGPTを活用するコツを紹介します。
具体的な手順をまとめているので、すぐに実行可能な内容です。
この記事を読み終える頃には、AIはより正確で頼れるパートナーになっているはずです。
それでは、さっそく始めていきましょう!
ChatGPTのような生成AIは、目的の結果を出力するためのコツがあります。
もちろん直感的にも使えますが、実務で使用する場合には質を高めることが重要です。
質を高めて意図した結果を出すには、以下の3つの手順を意識しましょう。
これらの手順を、体系的にまとめて、再現性のある手法として活用します。
そのための方法を、ここから具体的に解説していきますね。
もしChatGPTに登録していない場合は、無料プランでOKなので登録しておきましょう。
まず最初に、「どこに向かうのか」を決めます。
つまり、地図アプリで目的地を設定するようなイメージです。
ゴールが曖昧だと、どんなに高性能なAIでも迷子になってしまいます。
ゴールが決まったら、条件を箇条書きでリスト化します。
そのうえで、プロンプトとして設計します。
おすすめのフレームワークは、Nexus AI独自の「RTF-CCSF」です。
(Role / Task / Format / Constraints / Context / Samples / Flow)
「RTF-CCSF」以外にも、条件を整理する方法はあります。
以下の内容を参考にしながら、あなたのやりやすい方法を採用しましょう。
あなたは【役割】です。
【読者/対象】に向けて、【目的】を達成するための【成果物】を作成してください。
■条件
- トーン:【例:落ち着いた専門家・敬体】
- 文字数/構成:【例:600~800字、H2→H3→箇条書き】
- 必須要素:【例:課題→解決策→根拠→CTA】
- 禁止事項:誇張表現/曖昧語/専門用語の多用
- 表記ルール:用語統一「生成AI/生成AI」→「生成AI」に統一
■前提情報
- 読者像:【例:中小企業のWeb担当、初心者】
- 利用シーン:ブログ/LP/メール 等
- 参考資料:要点を箇条書きで貼付(URLは要約して渡す)
■出力形式
- まず「骨子(見出しと要点)」を出力
- 次に「本文」
- 最後に「CTA」
一度で完璧を狙わず、小さく回して詰めるのが最短ルートです。
編集者の視点で、変えてほしい点だけを端的に指示します。
刃を研ぐ:刃は研ぐたびに切れ味が増します。
文章も同じで、小さな研ぎ(微調整)の積み重ねが質を決めます
以下の観点で本文を自己点検し、各項目を5点満点で採点してください。
その後、合計点を2点以上上げるための具体的修正案を3つ提案してから、修正版本文を出力してください。
観点:目的適合/読者適合/構成/具体性/正確性
出力順:採点→改善提案→修正版
※思考プロセスを長文で説明させる必要はありません。
採点と短い根拠で十分です。
修正方針:
- 目的適合:CTAが弱い → 「無料相談」導線を明確化
- 読者適合:専門用語を中学生にも通じる語に言い換え
- 構成:結論先出し→根拠→事例→CTA の順に組み替え
- 具体性:抽象表現を3箇所、数値や事例に置換
- 正確性:不明確な主張は「出典不明」と注記
保持:導入の共感パートは現状維持
出力形式:本文のみ、最大400字
あなたはSEOに強いテクニカルライターです。
初学者向けに、以下の条件で導入文を書いてください。
- 300~350字、敬体、専門用語は平易に言い換え
- 共感→問題提起→解決の方向性→記事で得られる価値 の順
- 「プロンプト」「出力精度」「手順」という語を自然に含める
- 誇張表現はNG
このように評価→差分指示→再出力を2~3回繰り返すと、短時間で精度が整います。
実務で使用できるプロンプトの設計には、具体化が欠かせません。
では、なぜ具体的にする必要があるのでしょうか?
その理由とは、主に以下の3つがあります。
明確なプロンプトで、生成AIの誤解や間違いを防ぐことができます。
では、さらに詳しい内容を見ていきましょう。
AIの認識方法は、人間とは異なります。
そのため、曖昧語や抽象的な指示は、意図しない結果になりやすいです。
→ 範囲・定義・視点を具体化すると、解釈の幅が収束し、誤読が激減します。
カーナビに「その辺のカフェ」と言うと、駐車場がない店が設定されるかもしれません。
「博多駅から徒歩5分以内・静か・駐車場あり」と言えば、誤解は起きにくくなります。
情報が欠けると、AIは「もっともらしい補完」をします。
これがハルシネーション(意図しない間違い)の原因です。
→ 根拠の範囲・情報ソース・不明時の対応を決めると、補完を防ぐことができます。
新聞記者は裏取りができない情報は「関係者によれば」と記し、断定を避けます。
プロンプトでも「断定の条件」を明記すれば、無用な想像は抑えられます。
事実ベースで出力。
根拠が本文に存在しない場合、該当部分は「不明」と表示。
推測や仮定は使用しない。
AIは「何を良しとするか」の評価関数が曖昧だと、一般論に流れます。
→ 完成イメージ(フォーマット・トーン)と成否基準(成功条件・NG例)を示すと、出力が意図に収束します。
写真撮影で「良い感じに撮って」は、人によってイメージが異なるため難題です。
「バストアップ・被写体は左3分の1・逆光は避ける・背景ボケ強め・笑顔」と指定することで、ほぼ狙い通りに仕上がります
出力基準:
- OK:冒頭3文で読者の課題と解決方針が伝わる
- OK:段落ごとに1メッセージ/冗長な修飾なし
- NG:主語が曖昧・一般論で終わる・CTAが不明
まず成否判定のみを箇条書きで返答→続けてOKの本文を出力
ここでの結論は、可能な限りの「具体化」です。
具体化するイメージが湧かない場合には、チェックリストで一つずつ確認しましょう。
また、ここまで挙げたプロンプト例も参考になるはずです。
プロンプトや生成した結果は、一度で完璧に仕上がることはほぼありません。
ではどうすればいいかというと、フィードバックループ(修正改善)です。
生成された結果をもとに、さらに良い結果を導いていきます。
このフィードバックループこそ、人間の想像力が発揮される部分です。
より良いプロンプトによって、より良い結果が返ってきます。
ここでのポイントは、以下の3つです。
これらの手順を重ねることで、求める結果にどんどん近づいていきます。
では、詳しい内容を見ていきましょう!
修正の際にも、具体的な指示は非常に有効かつ重要です。
「何を/どこを/どの程度/何のために」を明示すると、無駄な再出力が減ります。
【修正対象】段落2(導入の直後)
【修正目的】CTAの明確化と具体性の強化
【変更内容】
- 文字数:現状から20%短縮
- 追加:数値根拠を1つ(例:〇〇の工数30%削減)
- 構成:結論先出し→根拠→CTAの順に並べ替え
【保持】トーン(落ち着いた敬体)、既存の固有名詞
【禁止】誇張表現/推測での記載
【出力形式】本文のみ、200〜230字
1回の調整で、完全に意図通りとなることはあまり多くありません。
修正の際には、「広く直す」より「狭く深く」が有効です。
3ラウンド程度の小回りで完成度が跳ね上がります。
以下の観点で本文を自己点検し、各項目を5点満点で採点してください。
その後、合計点を2点以上上げるための具体的修正案を3つ提案してから、修正版本文を出力してください。
観点:目的適合/読者適合/構成/具体性/正確性
出力順:採点→改善提案→修正版
指示:
「結論先出し→根拠→手順→CTAの順に再配置。冗長な表現を削除。」
指示:
「事例を1つ追加。“数値”を2つ入れて定量化(字数±5%)。」
指示:
「“落ち着いた専門家”の語彙に統一。口語を2箇所だけ残して親しみを維持。」
【保持】導入の共感パート、用語の定義
【削除】重複する一般論(2文)
【追加】具体事例(BtoBメール)120〜140字
【置換】「多く」「かなり」→ 数値表現(例:20〜30%)
保持/削除/追加/置換を明記することで、意図しない変更を防ぐことができます。
ハルシネーション対策にも有効なのが、参考資料やサンプルの提示です。
根拠(RAG的な参照)と完成形のサンプルを渡すと、ズレが激減します。
チャットGPTであれば、入力欄からファイルを添付することもできます。
ファイルとして用意できるなら、チャットGPTであれば添付して送信します。
ウェブサイト等から引用するなら、URLの提供よりも要点をまとめた方が良いでしょう。
※「要点を箇条書きで渡す」のがコツです。
AIの読解負荷が下がり、意図しない補完が抑えられます。
さて、具体的にAIに修正指示を出すには、どうすればいいでしょうか?
ここからは、先ほどのフィードバックループを事例として解説していきます。
3ラウンドの細かな修正についても、具体的な事例でより明確になるはずです。
以下の3つの事例を想定して、紹介していきますね。
初稿の課題:自社説明が長く、相手のベネフィットが後回し。CTAがぼやけている。
→ 期待する変化:スクロールせずに価値が伝わり、返信率のボトルネック(CTA不明)が解消。
初稿の課題:導入が長く、フックが弱い。視聴維持率が落ちる。
初稿の課題:機能説明のみで、使用シーンが見えない。返品条件が曖昧。
ここまで、生成AIで目的に合った結果の出力と、修正改善の方法を解説してきました。
目的に合った結果を出力する3つの手順は、以下の通りです。
この手順でChatGPTの生成を開始すれば、精度の高い出力が可能となります。
すでにお伝えしているとおり、重要なのは具体性と根拠を示すことです。
具体的な指示には、「RTF-CCSF」フレームワークが有効です。
根拠を示すためには、RAG的なアプローチとして、ファイル添付などが良いでしょう。
そして、さらに精度を高めるために、修正改善を繰り返します。
一度にすべてを修正するのではなく、必要な修正を個別に行うことが重要です。
3ラウンドの修正法を参考に調整することで、生成AIは真価を発揮します。
回答の精度が非常に高く、かつ効率的にテキストを生成可能です。
結論として、最終的には人間の手による調整が必要だということになります。
つまり、AIと人間が共同で動くことで、最もクオリティが高まります。
これからも、生成AIはさらに進化し続けていくでしょう。
将来においても、人間とAIの共創は大切なプロセスです。
当サイトは、AIと人間が繋がるコミュニティです。
このようなコミュニティに興味があれば、以下のリンクから参加できます。
ゴールや条件が曖昧なまま依頼するのが主な原因です。AIが自由に解釈してしまい、意図しない結果が増えてしまいます。
可能な限り具体化することです。定義・条件・成功基準を明確にし、OK例・NG例も添えると精度が安定します。
文章のゴールと用途(誰に、何のために、どの形式で)を明確に決めることです。
条件を整理し、役割・タスク・形式・制約・前提・サンプル・進行手順まで具体化して指示します。
用語や条件を明確に定義し、不明点は「不明」と記載させ、推測や補完を避けるよう指示します。
目的適合・読者適合・構成・具体性・正確性の5項目で採点し、改善点を具体的に指示します。
ほとんどの場合は難しいため、狭い範囲での微調整を2〜3回重ねることで完成度が大幅に向上します。
修正箇所・変更量・保持する要素・禁止事項を明示し、字数や件数など定量的に指定します。

【Nexus AI 代表】Web制作・デザイン・マーケティング・コンサルティング等の経験を積み、日本 AIコミュニティ Nexus AIを立ち上げる。AI技術を活用して、コミュニティ運営に役立てている。
変化を起こし続けるなら、その人生には意味がある。
よく使うAI:OpenAI(ChatGPT, OpenAI APIなど)
好きなゲーム:ウィッチャーシリーズ、サイバーパンク2077、Forza Horizonシリーズ、その他多数

Web制作・デザイン・マーケティング・コンサルティング等の経験を積み、ChatGPTコミュニティ Nexus AIを立ち上げる。AI技術を活用して、コミュニティ運営に役立てている。