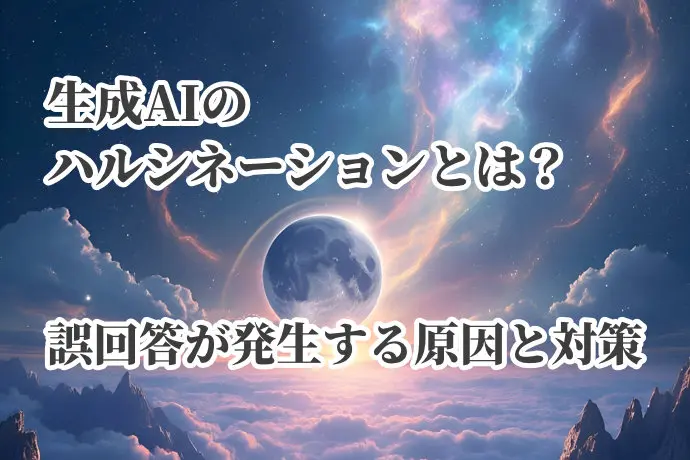

生成AIってすごく便利ですよね。
膨大な情報を持っていて、様々な処理をあっという間に行ってくれます。
ただし、現時点ではAIは万能ではありません。
たとえば、ハルシネーションという現象がよく起こります。
ハルシネーションとは、AIが間違った情報を生成する現象のことです。
この現象には、明確な原因と対策があります。
具体的な原因を知っておくことで、より適切に情報を扱うことが可能です。
AIをより便利に、賢く利用する方法を今のうちに習得しませんか?
この記事で、必要な情報をすべて得ることができます。
さっそく進めていきましょう!
「ハルシネーション(hallucination)」とは、生成AIが事実とは異なる情報をもっともらしく出力してしまう現象を指します。
「幻覚(hallucination)」という言葉のとおり、AIが“実在しないことを信じ込んで語る”ような出力が見られることから、このように呼ばれています。
たとえば、以下のような内容をAIが生成してしまうことがあります。
このような意図しない間違いを、「ハルシネーション」と呼びます。
ハルシネーションが起こることには、明確な原因があります。
そしてその「原因」とは、ある意味で意図された設計でもあります。
では、なぜそのような設計なのか?
生成AIの仕組みからひも解いていきましょう。
以下の原因を、より詳しく解説していきます。
生成AIでは、大規模言語モデル(LLM)が使用されています。
このモデルは、「次に来る単語を予測する」という仕組みで動いています。
たとえば、以下のような文を考えるとわかりやすいでしょう。
○○に続く言葉として、AIは「山」「山脈」「峰」などの可能性を確率的に評価します。
そのうえで、最も確率が高い(≒最もそれらしく見える)単語を選んで出力するのです。
この仕組みは、厳密には「正解を導く」ためのものではありません。
そうではなく、「自然な言語表現を生成する」ことに重きが置かれています。
そのため、本当に正しい情報かどうかは判断できないという性質が、ハルシネーションの根源といえます。
AIはあらゆる情報を知っているように感じられるかもしれません。
しかし、実際には「過去にインターネット上などに存在していたデータ」から学習しているにすぎません。
このことが、いくつかの重要な制約を生み出しています。
たとえば、2025年以降に起きた出来事について質問したとします。
この場合、AIは正しい答えを返せない可能性があります。
なぜなら、その時点のデータが学習されていない場合があるからです。
インターネットには、正確な情報があるとは限りません。
誤情報や偏った見解なども、多数存在しています。
AIは、上記のようなデータをすべてを「平均化して」学習します。
そのため、実際には存在しない情報や、曖昧な内容を真実のように語ることもあります。
AIは、質問が具体的であるほど正確に応答できます。
逆に、曖昧な質問をされると“想像で補って”回答を試みる傾向があります。
人間であれば、「話していた文脈」「相手の関心」などから補完できます。
しかし、AIにとってはまだ苦手な部分です。
このように、入力のあいまいさがAIの“誤回答”につながることも少なくありません。
AIは、プロンプト(入力文)と呼ばれる指示内容に大きく影響を受けます。
さらに、以下のようなパラメータも、ハルシネーションに関与します。
温度を高く設定すると、AIの出力はより創造的になります。
しかし同時に、事実性の精度は下がるため、間違いやすくなるのです。
出力長(トークン制限)によって、AIが上限を超えた情報を切り捨てることがあります。
その際、切り捨てた情報の内容を“想像”して補完してしまう場合があります。
最後に見落とされがちな要素として、そもそも生成AIが“間違いを避けるようには設計されていない”という事実があります。
OpenAIをはじめとするAI開発者たちは、AIを「創造性と柔軟性のあるパートナー」として設計しています。
そのため、完全な正確性よりも、「人間のような自然な言葉運び」や「多様なアイデアの提示」を重視してきました。
つまり、ある意味でハルシネーションは、“副作用”ではなく“意図された設計の一部”といえる側面もあるでしょう。
チャット型のAIは、非常に高度なやり取りを可能としています。
まるで、AIが人間のように「意味を理解している」と感じてしまうこともあるでしょう。
しかしそれは、あくまでも“言語表現が巧み”だからにすぎません。
実際には、AIは単語同士の関連性を数値として計算しているだけです。
「意味の理解」や「意図の把握」は行っていないのです。
このような誤解があると、「AIが理解した上で間違った判断をした」と思いがちです。
しかし、実際には理解していないからこそ、自然に嘘をつくという状況が生まれます。
ChatGPTは、テキスト以外の情報も扱える「マルチモーダルAI」です
この場合は、画像、音声、動画などの要素からもハルシネーションが発生します。
これはつまり、視覚情報とテキスト情報の結びつきがまだ発展途上だということです。
また、人間の認識力には現時点では及ばないことを意味しています。
ここまで、ハルシネーションの原因を紹介してきました。
AIの設計上、ハルシネーションを完全に避けることは難しいといえます。
しかし、適切な使い方や工夫によって、その発生を大きく抑えることが可能です。
ここでは、生成AIを使う上でぜひ身につけておきたい対策を4つの観点から紹介します。
AIに与える指示(プロンプト)は、文章の構造、語彙、曖昧さの排除が極めて重要です。
明確かつ具体的に伝えることで、AIは誤った“想像”を避け、より正確な応答をしやすくなります。
このように、「誰が・いつ・どの分野で」などの条件を明確にすることで、AIは適切な情報に近づきやすくなります。
また、プロンプトに出力形式(例:箇条書き・表形式)や文字数制限を加えることで、ハルシネーションを防ぎつつ整った情報を得ることができます。
AIからの回答は、一見もっともらしく見えるが間違っていることがあるため、ファクトチェックが欠かせません。
特に学術的・医療的・法律的な内容では、AIの出力を鵜呑みにせず、信頼できる一次情報を確認する姿勢がとても重要です。
ChatGPTのような生成AIには、モデルごとに得意・不得意があります。
たとえば、GPT-4はGPT-3.5に比べて事実性や論理構造が強化されています。
ただし、それでも誤情報が出る可能性はあります。
また、創造性を求める場合は温度を上げ、正確性を求める場合は温度を下げるなどの使い分けも重要です。
業務用途などで正確性が最優先される場面では、企業が独自に調整したカスタムLLMや、RAGを組み合わせたハイブリッド型のモデルを利用する方が安全です。
RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、AIが自らの知識ベースに頼らず、外部の最新情報を参照しながら回答を生成する仕組みです。
たとえば、以下のような情報がすでに用意されているとします。
社内マニュアル
最新ニュース記事
論文・PDF文書
上記の情報をAIに参照させることで、古い情報や誤解を避けた回答が可能になります。
このように、RAGは特に情報更新が頻繁な分野での活用に向いています。
多用な分野に対応できるので、今後ますます注目される技術となるでしょう。
実際に、AIがどのようにハルシネーションを起こすのか──
それを具体的なケースと共に5つのステップで解説します。
体験を通じて理解を深められるようお伝えします。
源頼朝と織田信長は同じ時代に活躍した武将ですか?
このような質問は一見シンプルですが、「前提に誤りが含まれている」内容です。
そのため、生成AIがハルシネーションを起こしやすい典型例です。
はい、源頼朝と織田信長は共に戦国時代に活躍した武将であり、日本の歴史に大きな影響を与えました。源頼朝は鎌倉幕府を開き、織田信長はその後の戦国大名として中央集権の基礎を築きました。
このように、非常にそれらしい語り口で誤情報が提示されることがあります。
語調に自信があるため、知識がない読者は信じてしまう可能性が高くなります。
→ 実際には約400年の時代差があり、直接の関わりは一切ありません。
AIは「どちらも有名な武将」という共通項によって、時間軸の整合性を無視した出力を生成しています。
「源頼朝 年代」「織田信長 年代」などで検索すると、すぐに時代の差が確認できます。
「この2人が本当に同じ時代に存在していたら、歴史の教科書で同時に紹介されていたのでは?」という直感的な疑問も大切です。
Wikipediaや公的な歴史サイトで事実確認を行うのが有効です。
誤解を生みにくい、明確で中立的な質問に変えることで、ハルシネーションの発生確率を下げられます。
源頼朝と織田信長は同じ時代に生きていましたか?
それぞれの活躍した時代について教えてください。
このように時代や人物の関係を分けて質問することで、モデルが自動的に「比較対象」として認識し、より正確な出力をする傾向があります。
このケースは、私が実際に遭遇した事例です。
技術者向けのやや高度な内容となります。
PHPでREST APIを使用するスクリプトを、生成AIに作成してもらったときのことです。
公式ドキュメントに存在しないエンドポイントを含んだコードが生成されました。
このような「ありそうだけど実在しない情報」を出力する現象こそが、AIによるハルシネーションです。
では、どのような流れで解決したのか詳しくご紹介します。
PHPで、〇〇というREST APIを使って、特定ユーザーの詳細情報を取得するスクリプトを書いてください。
※ここでの「〇〇」は、実在する外部のREST API名(例:架空のCRM API)を想定しています。
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => 'https://api.example.com/users/details?id=1234',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
'Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN',
'Content-Type: application/json'
),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
?>
以下に貼り付けたAPIドキュメントの中にあるエンドポイントのみを使用して、PHPで該当スクリプトを書いてください。
ドキュメント外の内容は使用しないでください。
コードの出力結果を鵜呑みにせず、毎回、公式ドキュメント・エラーメッセージ・動作確認の3点で検証することが重要です。
私の場合は、RAGを活用して実在するエンドポイントのみを明示的に指定しました。
これにより、公式ドキュメントに準拠したスクリプトが完成しました。
エラーハンドリングも網羅した、非常に堅牢なスクリプトです。
この事例は、生成AIの“言語パターンとしての整合性”を優先する性質に起因しています。
つまり、AIは「よくあるAPI設計」の型から「それっぽい答え」を作るのが得意です。
しかし、事実や仕様の正確性までは保証していません。
とはいえ、逆に言えば——
AIの出力を公式ドキュメントなどの“正しい知識”で補強する設計(RAG)を取れば、極めて実用的なツールにもなり得ることを、この事例が示しています。
| 要素 | 難しさ | 対策 |
|---|---|---|
| 温度 | 高すぎると創作に傾く | 0.3〜0.5で安定性重視 |
| トークン長 | 長すぎると文脈を忘れる | 出力内容を分割して依頼 |
| プロンプト | 曖昧だと誤情報が混ざる | 明確に意図と制限を伝える |
ここまで、ハルシネーションの原因と対策について詳細に解説してきました。
これらの内容を踏まえておくことで、より適切なアウトプットが可能になります。
最後に、ハルシネーションの定義について一覧表でまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | AIがもっともらしいが虚偽の情報を生成すること |
| 原因 | 確率的な出力、知識の限界、曖昧な入力、設計思想 |
| 対策 | ファクトチェック、文脈を明確にする、RAGの活用 |
| 実務応用 | 出力結果の確認と再設計を習慣にする |
| 本質理解 | LLMは「知識の保有者」ではなく「文の予測者」 |
ハルシネーションは単なる「間違い」というわけではありません。
生成AIの構造、限界、そして設計思想の複合的な結果です。
だからこそ、あなた自身が理解し、活用方法を工夫することが不可欠です。
AIの特性を理解することで、創造的に活用する力が磨かれていきます。
ハルシネーションは、AIが見せる幻想ともいえるでしょう。
しかし、その幻に惑わされず、真実を見極めるのは人の知性と判断力です。
あなたが光となり、AIの力をより正確に導くことができますように。
当サイトは、AIでより良い未来を創造するコミュニティを運営しています。
興味があれば、以下のページで詳細を確認できます。
生成AIが実際には存在しない情報を、あたかも事実であるかのように出力する現象です。
言語モデルは「意味」よりも「文脈上もっともらしい語の並び」を予測しており、事実確認の機能を持っていないためです。
特に以下のような場面で発生しやすいです。
専門的・マイナーな情報
ファクトチェックが難しい話題
曖昧な質問や長文指示
いいえ、非推奨です。ハルシネーションが含まれている可能性があるため、必ず信頼できる情報源で検証してください。
完全には防げませんが、プロンプトを明確にしたり、信頼性の高い情報でファインチューニングされたモデルを使用することで減らすことは可能です。
ハルシネーションは意図的な虚偽ではなく、AIの限界に起因する誤情報です。AIは「騙そう」としているわけではありません。
はい。現在のあらゆる大規模言語モデルには、程度の差こそあれハルシネーションの可能性があります。
架空の論文名を提示したり、存在しない法律や人物について言及するなどが代表例です。
AIの出力をそのまま鵜呑みにせず、一次情報(公的機関・論文・ニュースメディア等)でクロスチェックすることが重要です。
完全な解決には至っていませんが、RAG(検索との統合)やファインチューニング技術により、大幅な軽減が期待されています。

【Nexus AI 代表】Web制作・デザイン・マーケティング・コンサルティング等の経験を積み、日本 AIコミュニティ Nexus AIを立ち上げる。AI技術を活用して、コミュニティ運営に役立てている。
変化を起こし続けるなら、その人生には意味がある。
よく使うAI:OpenAI(ChatGPT, OpenAI APIなど)
好きなゲーム:ウィッチャーシリーズ、サイバーパンク2077、Forza Horizonシリーズ、その他多数

Web制作・デザイン・マーケティング・コンサルティング等の経験を積み、ChatGPTコミュニティ Nexus AIを立ち上げる。AI技術を活用して、コミュニティ運営に役立てている。